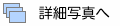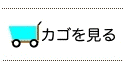Lobopyge / ロボピゲ
Lobopyge (ロボピゲ)は、世界中の三葉虫の中で最も産出量が少ない存在のorder (目/もく)である、Lichida (リカス目)に属している三葉虫です。そのため、このLobopyge (ロボピゲ)も、大きく出入りのある尾板や特徴的な頭部など、一般的な三葉虫の体とはかけ離れているLichida (リカス目)の特徴を持っています。このモロッコ産のものは大きくとも2cm程度ですので、カナダのオルドビス紀の地層から産出するHemiarges (ヘミアルゲス)や、ボリビアのデボン紀からのAcanthopyge (アカンソピゲ)などの小さめのLichida (リカス目)の仲間と言えそうです。特にこのモロッコ産のLobopyge (ロボピゲ)は、産出するその多くが弓状に反っている体勢であることから、生きている時は頭を上にして海底の地中に潜っていたのかもしれません。